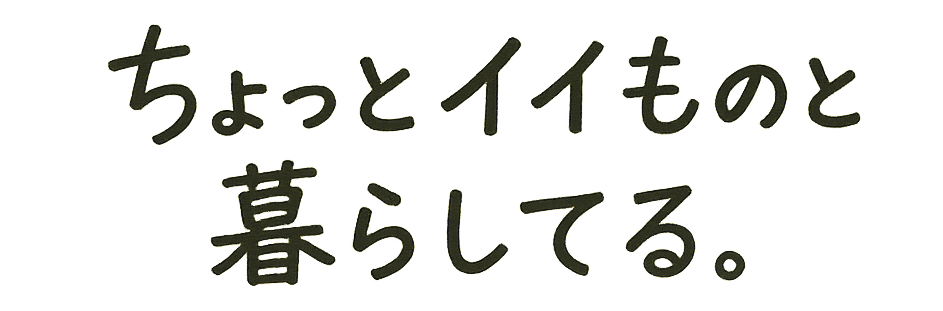適応障害で休職を申し出たとき、会社はどんな対応をするべきなのか、不安に感じていませんか?
- 休職を申し出たが、会社からの説明や案内がほとんどない
- 対応が不十分で、このまま療養できるのか不安
- 一般的な会社の対応や正しい手続きを知っておきたい
この記事でわかること
- 会社の対応が十分かどうかは、制度説明と産業医面談の有無で判断できる
- 不十分な対応には、証拠を残し外部機関へ相談することが有効
- まずは自分の回復を最優先し、迷わず休職に入ることが結果的に周囲を守る
この記事では、一般的な会社の対応から、不十分な場合の動き方、そして筆者の実体験まで詳しく解説します。「自分の会社の対応は適切か」を冷静に見極め、必要な行動をとるための指針として、ぜひ最後まで読んでください。
適応障害で休職を申し出たときの一般的な会社の対応
適応障害で休職を申し出た場合、会社には一定の対応フローがあります。
これは就業規則や労働基準法、労働安全衛生法などに基づいて行われるもので、必ずしも会社独自の裁量で決められるわけではありません。
一般的な流れは以下の通りです。
- 医師の診断書の提出依頼:診断名や休職期間、就労制限の有無が明記された診断書を求められるケースがほとんどです。
- 産業医や保健師との面談:労働安全衛生法に基づき、産業医面談を行う場合があります。面談で現状や復職見込みを確認します。
- 休職制度の説明:就業規則に定められた休職期間や給与の有無(傷病手当金など)、手続きの流れを案内されます。
- 労務管理上の調整:業務の引き継ぎや社内連絡、必要に応じてメールや社内システムのアクセス制限など。
この時点で重要なのは、口頭だけでなく、書面やメールで正式な案内をもらうことです。後々「そんな説明はしていない」と言われるリスクを防げます。
実際に多い会社の対応パターンと注意点
適応障害で休職を申し出たとき、会社の対応は大きく分けて「手厚い対応」と「不十分な対応」に分かれます。
手厚い対応の例
- 人事部や上司が迅速に休職制度や公的給付制度を案内してくれる
- 産業医面談を複数回実施し、状況に合わせて対応を調整
- 復職支援プログラム(リワーク)への参加を積極的に勧める
不十分な対応の例
- 休職申請を渋る、もしくは「自己都合退職」を勧める
- 就業規則や制度の説明がない、口頭のみで曖昧
- 産業医面談を行わず、自己判断で対応を決める
不十分な対応をされると、傷病手当金の受給が遅れる、復職のための環境調整が行われないなどの不利益が生じます。
特に「自己都合退職」を勧められた場合は注意が必要で、後の生活に大きく影響します。
会社の対応が不十分と感じたときの対処法
会社の対応が不十分な場合、まずは記録を残すことが最優先です。
やり取りのメール保存や、会話の録音、説明資料の保管が後々の証拠になります。
相談窓口の活用
- 労働基準監督署:労働基準法違反の可能性がある場合に相談可能
- 労働局の総合労働相談コーナー:制度説明不足や不利益取扱いについて相談できる
- 労働組合(社内・外部):会社との交渉を代行してくれる場合あり
医師の診断書の効力を最大限に活用する
診断書は法律的にも強い証拠力があります。
会社が休職を拒否する理由が「業務が忙しいから」「前例がないから」といったものであれば、法的根拠に欠けます。
診断書を盾に冷静に対応しましょう。
また、口頭でのやり取りは避け、必ず書面・メールで残すことで、後から事実関係を証明できます。
筆者の実体験:診断書取得から休職までの流れ
私自身も限界を感じ、心療内科を受診しました。
その日のうちに「適応障害」の診断が下り、即日で診断書が発行されました。
診断書は原則として発行日から効力がありますが、医師と相談すれば開始日を数日後に調整することも可能です。
診断書を受け取った後、職場の保健師に提出。保健師の同席のもと、上長と人事に診断書を渡しました。
内容が「即日からの業務停止」だったため、その瞬間から業務は全てストップ。
引き継ぎも行わず、部署の上長が対応する形になりました。PCや業務用スマホは会社に置き、そのまま自宅療養に入りました。
休職に入ってからは、月1回程度の保健師面談と、週1回の心療内科診察を継続。面談では「復帰の時期」や「復帰の形」について話し合っています。
当初は、引き継ぎせずに即日休むことに抵抗があり、「周りに迷惑がかかるのでは」と迷いました。
しかし、帰宅後すぐに寝込み、目が覚めたのは約24時間後。心身ともに限界を超えていたことを痛感しました。
無理をして働き続ければ、その分回復は遅れます。結果的に会社や周囲にも負担がかかります。
まずは自分を守ることが、最終的には周りを守ることにもつながります。
あなたがいなくても会社は回ります。だからこそ、迷わず休む決断をしてほしいと思います。
まとめ
- 一般的な会社の対応フロー:診断書提出 → 産業医面談 → 休職制度の説明 → 労務調整
- 不十分な対応例:休職拒否、制度説明なし、産業医面談省略
- 対処法:証拠を残す、労働局・労基署・労組へ相談、診断書を最大限活用
適応障害で休職する際は、会社の対応が適切かどうかを冷静に見極め、自分の身を守る行動をとることが何より重要です。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「適応障害の診断書を出したのに、会社がまともに取り合ってくれない…」 そんな悩みを抱えていませんか?[…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 適応障害って、いつ治るの?――診断された直後や休職中に何度もよぎる、この不安。 私も同じ疑問を抱えな[…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「最近、集中が続かない」「仕事に行きたくない」「なんとなく毎日つらい」 そんな風に感じることが増えて[…]