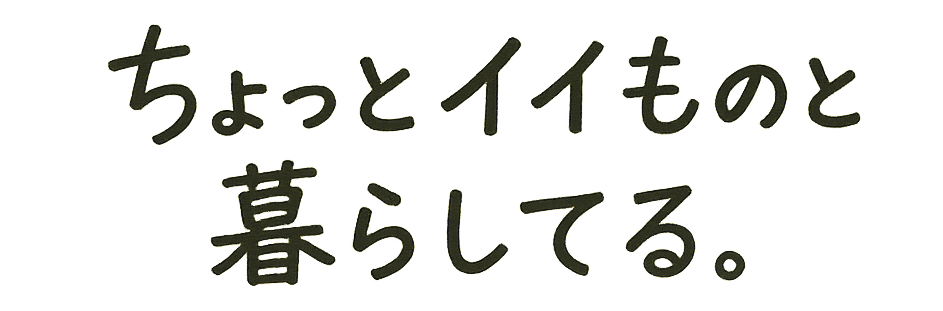上司の言動が原因で体調を崩し、適応障害と診断された──
そんな状況で、どう会社や人事に伝えればいいのか悩んでいませんか?
- 感情的にならずに、事実として冷静に伝える自信がない
- 誰に、どの順番で話すべきか迷っている
- 伝えたことで人間関係がさらに悪化しないか不安
この記事でお伝えする結論は以下の3つです。
- 感情をぶつけるのではなく、事実と体調の変化を簡潔に整理して伝えることが最も効果的
- 上司に直接言いづらければ、産業医・人事・上長の上司、または隣の部署の部長など信頼できる第三者に伝える
- 人間関係を恐れるのではなく、まずは自分の安全と健康を守ることを最優先にする
この方法なら、状況を正しく理解してもらいやすく、必要な対応も受けやすくなります。
また筆者が実際に行った行動をもとに、「こうしておけばよかった…」と感じた反省も含めて、最適な行動をまとめています。
適応障害の原因が上司の場合、なぜ伝え方が重要なのか
上司が原因で適応障害になった場合、「どう伝えるか」でその後の対応や環境改善が大きく変わります。
感情的に伝えてしまうと、単なる人間関係のトラブルと受け取られたり、「あなたにも問題があるのでは?」と誤解されるリスクがあります。例えば、日々の発言や態度により強いストレスを受けていたとしても、「あの人が嫌い」「耐えられない」とだけ伝えると、会社側は個人的な感情のもつれと判断してしまうことがあります。
一方で、「いつ」「どこで」「どのような発言・行動があったか」「それによって体調がどう悪化したか」を冷静に整理して伝えれば、状況は大きく変わります。人事・産業医・上層部は客観的な情報をもとに判断や対応を行うため、証拠や経緯が明確であればあるほど、あなたに有利な方向で動いてくれる可能性が高まります。
さらに、適応障害は見た目では分かりづらく、「本人の気持ち次第で回復できるのでは?」と誤解されやすい病気です。だからこそ、医学的な診断書や、第三者が確認できる事実をもとに伝えることが、理解と対応を得る近道になります。
つまり、「冷静な伝え方=自分を守るための武器」です。適切な伝え方を選ぶことで、環境改善や配置転換、休職といった選択肢も現実的に検討してもらえる可能性が高まります。
伝える前に整理しておくべきこと
ここで紹介する内容をすべて実行できれば理想ですが、実際には追い込まれている状況で全てをまとめるのは至難の業です。
無理に完璧を目指さず、自分にできそうな部分だけ実践するだけでも大きな前進になります。
結論:事実・体調・希望(どうしてほしいか)の3点を紙に落としてから臨むと、話し合いがスムーズになります。
1) 事実の整理(時系列)
- いつ:年月日・時間(例:2025/06/12 10:00)
- どこで:会議室、デスク周り、チャット上など
- 誰が/誰に:上司の氏名・ポジション、自分、同席者
- 何を言われ/され:具体的な発言・行為(可能な限り原文)
- 証拠:メール・チャットログ・議事録・録音メモ・日記・勤怠記録
ミニテンプレ:
【日時】2025/06/12 10:00 【場所】第2会議室 【関係者】上司A、本人B
【発言/行為】「〇〇はお前の怠慢」など(原文)
【直後の状況】手の震え、会議中退席 【証拠】Teamsログ/同席者Cが同席
2) 体調の変化(医学的根拠)
- 診断書:病名(適応障害)、診断日、就業配慮の要否
- 症状ログ:睡眠障害、動悸、吐き気、朝起きられない等の頻度・強度
- 受診歴:受診日、医療機関名、処方(可能な範囲で)
症状ログ(例):
【6/10】3時中途覚醒/動悸10分 【6/12】面談後に吐き気/手の震え 【6/14】出勤困難
3) 希望(会社に求めたいこと)
- 短期:上司Aとの直接接触の一時停止、配置変更の検討、在宅・時差勤務
- 中期:担当替え、席替え、評価関与の分離、産業医面談の継続
- その他:第三者同席でのヒアリング、再発防止策の提示
4) 客観性を高める「証拠の棚卸し」
| 証拠の種類 | 入手場所 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| メール/チャットログ | Outlook/Teams/Slack | 日時・原文・宛先・スレッド全体 |
| 会議記録/議事録 | 共有ドライブ/議事録ツール | 発言者・要点・決定事項 |
| 勤怠/面談記録 | 勤怠システム/人事面談記録 | 遅刻・早退・休職勧奨の有無 |
| 第三者の証言 | 同席者・同僚 | 見聞きした事実(主観ではなく客観) |
| 医療書類 | 医療機関 | 診断名・就業配慮の要否・期間 |
5) 伝達ルートと順番を事前に決める
- 推奨順:産業医/人事 → 上長の上司(必要に応じて) → 当該上司(第三者同席)
- 直属に言いづらい場合は、人事・産業医・隣部署の部長など第三者から着手
- 面談は必ずメモ(後日、要点をメールで議事録化)
6) 面談用の「ひとこと要約」の作成
30秒版(例):
「〇月から上司Aの〇〇という発言/対応が続き、睡眠障害などの症状が悪化。医師により適応障害と診断されています。当面の接触回避と配置変更の検討、産業医面談の継続をご相談したいです。」
7) リスク管理
- 面談は可能なら第三者同席(人事/産業医)
- 記録は1か所に集約(日付フォルダ/クラウド)
補足:上司の発言を録音しておく
日ごろから上司の発言や対応に疑問を持っている場合は、録音して証拠を残すことが最も確実です。録音データはそのまま提出するか、文字起こしして提出しましょう。ただし、自分で録音を聞き直すのは精神的負担が大きいため、生成AIでの文字起こしか、信頼できる第三者に任せることをおすすめします。
ここまで多くのことを書きましたが、一つでも実践できることがあれば必ず行ってください。それがのちに、あなたの身を守る大切な盾になります。
伝える相手別のポイントと例文
結論:感情をぶつけるのではなく、事実と体調の変化を簡潔にまとめ、相手に応じて言葉を調整することが大切です。
1) 会社・人事・産業医に伝える場合
会社や人事、産業医には、客観的で具体的な情報が必要です。感情表現を抑え、「いつ」「何があった」「どう体調に影響した」「どうしてほしいか」の4点を短くまとめます。
例文:
「〇月から上司Aによる〇〇という発言や対応が続き、睡眠障害や動悸などの症状が悪化しました。医師から適応障害と診断を受けています。当面の接触回避と配置変更のご検討をお願いします。」
2) 家族に伝える場合
家族には状況と体調を理解してもらい、サポートをお願いするのが目的です。詳細な証拠よりも、現状と困っていることを率直に共有します。
例文:
「上司からの言動が続いていて、体調を崩してしまった。医師からは適応障害と診断された。今は会社に対応をお願いしているけど、しばらく家でも休養を優先したい。」
3) 同僚に伝える場合
同僚への共有は必要最低限にとどめ、噂や対立を避けるよう配慮します。協力が必要な場合は、簡潔に背景とお願いを伝えます。
例文:
「最近体調を崩していて、産業医や人事と話をしている。少し仕事を調整することになるかもしれないけど、よろしくお願いします。」
4) 共通の注意点
- 感情的な表現や人格批判は避ける
- 事実+体調の変化+希望(どうしてほしいか)の3点でまとめる
- 可能なら第三者同席や記録(音声録音・メモ・メール)を残す
伝えるときの注意点
結論:感情に流されず、事実を軸に話し、証拠と記録を必ず残すことがあなたを守ります。
1) 感情的・攻撃的な表現は避ける
「〇〇が嫌い」「もう耐えられない」といった感情的な言葉は、相手に防御反応を生みやすく、冷静な対応を阻害します。事実を淡々と述べることで、相手の受け取り方も変わります。
2) 「いつ」「どこで」「何をされた(言われた)」「その結果どうなった」を必ずセットで伝える
この4点を押さえると、話が具体的かつ客観的になり、相手が状況をイメージしやすくなります。日付や場所は特に重要です。
3) 言葉だけでなく、証拠や記録を添える
メールやチャットのスクリーンショット、会議議事録、勤怠記録など、証拠があると説得力が一気に高まります。録音データや文字起こしも有効です。
4) 事前に話す順番を決めておく
伝える内容が整理されていないと、本来伝えたいことが抜けてしまいます。紙やスマホに話す順序を書いておくと、落ち着いて話せます。
5) 必要に応じて第三者に同席してもらう
人事・産業医・信頼できる上司などの第三者が同席すると、言った/言わないのトラブル防止になります。
6) 面談は必ず記録を残す
できる限り面談は音声録音を残しましょう。言った言わない問題の回避や、後からの確認や証拠として活用できます。
もし会社が動いてくれない場合の選択肢
結論:社内で改善が見込めないときは、外部の機関や法的手段を使って、自分の健康と安全を守る行動をとりましょう。
1) 労働局の総合労働相談コーナー
全国の都道府県労働局には、労働環境の改善やハラスメント対応について無料で相談できる窓口があります。匿名での相談も可能です。
2) 労働組合への相談
会社に労働組合がある場合は、組合を通じて交渉してもらえます。加入していない場合でも、外部のユニオンに加入してサポートを受けられます。
3) 弁護士への相談
法的措置が必要な場合や証拠の活用方法について、労働問題に強い弁護士に相談します。初回相談は無料のケースもあります。
4) 医師と連携して休職や配置転換を申請
医師の診断書をもとに、休職や部署異動を正式に申請します。健康保険や傷病手当金などの制度も併せて確認しましょう。
5) 転職を視野に入れる
改善が見込めず、精神的負担が大きい場合は、転職を検討するのも一つの選択肢です。転職活動は在職中から少しずつ始めると安心です。
6) 必要に応じて複数の手段を並行して進める
社内外のサポートを同時に使うことで、より早く状況改善を目指せます。「一人で抱え込まないこと」が何より大切です。
まとめ
上司が原因で適応障害になった場合、伝え方ひとつでその後の対応や環境が大きく変わります。
最後に、この記事でお伝えした結論をもう一度整理します。
- 感情をぶつけず、事実と体調の変化を簡潔に整理して伝えることが最も効果的
- 直属に言いづらい場合は、産業医・人事・上長の上司、または信頼できる第三者に先に相談する
- 一つでも実践できる行動を必ず行い、それを証拠として残すことで、後に自分を守る大きな盾になる
完璧を目指す必要はありません。
できるところから一歩ずつ行動に移すことで、あなたの安全と健康を守る力になります。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「最近、集中が続かない」「仕事に行きたくない」「なんとなく毎日つらい」 そんな風に感じることが増えて[…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「適応障害の診断書を出したのに、会社がまともに取り合ってくれない…」 そんな悩みを抱えていませんか?[…]