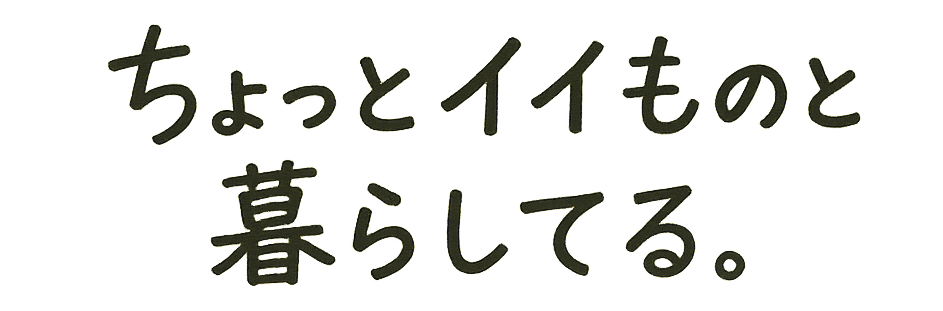適応障害って、いつ治るの?――診断された直後や休職中に何度もよぎる、この不安。
私も同じ疑問を抱えながら、治療と休養を続けてきました。
ここでは、回復までの目安、長引く/早く回復するケースの違い、そして復職の判断材料(特に睡眠)を私の実体験を交えて整理します。
焦る気持ちを少しでも軽くして、「次に何をすべきか」を一緒に見極めていきましょう。
この記事でわかること
- 回復は個人差が大きいが、「睡眠」と「環境」が整わなければ長引く
- 「3か月以上の休職診断」は重症サイン。焦らず治療を最優先に
- 睡眠が安定しない復職は再発リスク大。医師に正直に伝え、必要なら延期を
適応障害はいつ治る?回復期間の目安
適応障害の回復期間は数週間で改善する人もいれば、数か月〜半年以上かかる人もいます。
共通するのは、原因となったストレス要因から離れられるか、そして睡眠・食事・生活リズムが整うかで回復スピードが大きく変わるという点です。
大切なのは「時間が解決する」のを待つより、環境調整(異動・配置転換・距離を取る)と生活習慣の立て直しを同時並行で進めること。
これができると、症状の波はあっても徐々に安定していきます。
注意:気分の落ち込みや不眠、動悸、食欲不振などが強い場合は、自己判断せず医療機関を受診してください。症状が急に悪化することもあります。
早く回復するケース・長引くケースの違い
早く回復するケースの特徴
- ストレス要因から物理的に離れられた(部署異動・在宅・休職など)
- 早期に睡眠・食事・日中の活動量が安定した
- 医師・カウンセラーとの相談が継続でき、薬物療法や心理療法を適切に継続
- 家族・友人・職場など、最低限の支えがある
長引くケースの共通点
- ストレス要因が残ったまま(同じ部署・同じ人間関係)
- 睡眠障害や不眠が続く
- 焦って復職・社会復帰し、再度体調を崩す
- 生活リズムや活動量が乱れたまま
休職期間の目安と考え方
筆者のケースでは、診断時に3か月以上の休職という診断書が出されました。
会社の保健師によると、3か月以上の診断書は「よっぽどの重症」と捉えたほうがよいとのことです。
休職期間は一律で決められるものではありませんが、医師としっかり相談し、
「症状が落ち着くまで」ではなく「社会復帰できるレベルまで」を目安に考えることが大切です。
復職のカギは睡眠にある
私が実感しているのは、睡眠サイクルが整っていない状態では復職はほぼ不可能ということです。
3か月休職した現在でも、就寝・起床時間が日によってばらつきがあり、朝の起床が安定しません。
この状態では、出勤や日常生活を安定して送ることが難しいため、復職を延期する予定です。
医師も「睡眠の安定は復職判断の重要な指標」としており、早寝早起きが自然にできるようになってからがスタートラインです。
無理して復職しない勇気
適応障害では、「もう大丈夫」と自分や周囲を納得させたくなる瞬間があります。
しかし、医師に嘘をついて復職時期を早めるのは危険です。
無理に復職して再びつぶれると、休職期間はさらに延び、精神的ダメージも大きくなります。
私自身、今回の休職で「一度でしっかり治す」覚悟を持つことの大切さを学びました。
焦らず、医師と正直に向き合い、確実に回復させることが再発防止の第一歩です。
まとめ
- 適応障害の回復期間は人によるが、数週間〜半年以上かかる場合もある
- 睡眠・生活リズムの安定が復職の最重要ポイント
- 無理な復職は再発リスクが高く、結果的に休職期間が延びる
焦る気持ちは自然なことですが、回復のためには「今は治療を優先する」ことが未来の自分を守ります。無理をせず、医師と二人三脚で確実な回復を目指しましょう。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「朝起きれない」「やる気が出ない」「頭が働かない」── 以前の自分なら普通にできていたことが、なぜか[…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「適応障害って、弱い人間がなる病気でしょ?」そんな言葉を耳にしたことはありませんか? 結論から言いま[…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「適応障害の診断書を出したのに、会社がまともに取り合ってくれない…」 そんな悩みを抱えていませんか?[…]