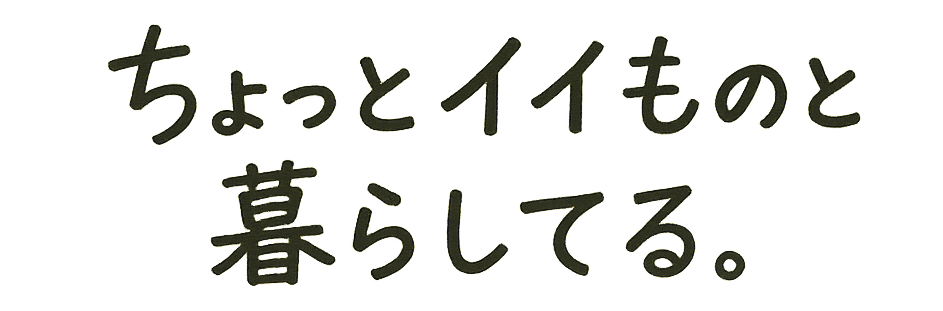最近、やたらと眠ってしまう日が続いていませんか?
- 仕事終わりや休日は一日中寝てしまい、何もできない
- 夜はうまく眠れないのに、日中は強烈な眠気に襲われる
- 気づけば生活リズムが完全に崩れている
このような状態が続くと、「ただの疲れ」ではなく、適応障害などメンタル不調のサインである可能性があります。
この記事では、筆者が実際に適応障害で寝すぎる・中途覚醒・早朝覚醒を経験したときの記録と、そこから回復するまでに効果的だった方法を紹介します。
特に筆者の経験上、日光浴は回復のカギでした。同じような悩みを抱えている方に、少しでも参考になれば幸いです。
適応障害と睡眠の関係
適応障害になると、睡眠パターンに大きな乱れが生じることがあります。具体的には、
- 寝すぎてしまう(過眠)
- 途中で何度も目が覚める(中途覚醒)
- 早朝に目が覚めて眠れない(早朝覚醒)
これは強いストレスによって自律神経のバランスが崩れ、体内時計や睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌リズムが乱れることが原因です。
睡眠の異常は、心身が限界に近づいているサインであり、放置すると症状が悪化する可能性があります。
筆者の場合も、最初は中途覚醒や早朝覚醒から始まり、その後日中の強烈な眠気と休日の過眠に悩まされるようになりました。
筆者の体験談
私の場合、適応障害の症状は睡眠の異常から始まりました。
最初に出たのは中途覚醒と早朝覚醒。夜中に何度も目が覚め、朝は必要以上に早く目が覚めてしまうため、常に寝不足の状態でした。
その結果、日中はとにかく眠くて仕方がない。仕事中も「1秒でも横になりたい」と思い、昼休みは食事をせず会議室で寝る、トイレで数分だけ仮眠を取るなど、とにかく眠気を優先するようになっていました。
休日や仕事終わりは、ほぼ死んだように眠り続け、何もできない日が続きます。夜は逆にうまく眠れず、悪循環に陥りました。
休職してからの最初の1週間は、ほぼ一日中寝て過ごす状態。「眠り続ける」ことでしか体を守れなかったように思います。
しかし休職を続けるうちに少しずつ体力が戻り、日中に目が覚めていられる時間が増えていきました。
寝すぎが危険なサインである理由
一時的な寝すぎは疲労回復のために必要なこともありますが、長期間続く場合は要注意です。
- 日常生活に支障をきたす(仕事・家事・学業がこなせない)
- 夜眠れない悪循環につながる
- 心身のSOSサインである可能性が高い
適応障害では、ストレスにより脳や自律神経が疲弊し、睡眠のリズムが崩れます。その結果、「眠らないと回復できない」状態が続くのです。
寝すぎが続くのは、心と体の限界が近いことを示す危険信号。放置すれば、うつ病などより重い症状へ進行する可能性もあります。
筆者自身も、「夜眠れないのに日中は極端に眠い」という状態が続いたとき、メンタル崩壊寸前だと感じました。
寝すぎが続いたときの対策
寝すぎの原因が適応障害などメンタル不調の場合、根本的な解決には医療機関の受診が欠かせません。そのうえで、日常生活でできる工夫も取り入れると回復が早まります。
- 医療機関を早めに受診する(心療内科・精神科など)
- 睡眠時間や生活リズムを記録し、自分の状態を可視化する
- 日中に軽い運動やストレッチを取り入れる
- 日光浴を習慣にする(体内時計を整え、気分を安定させる効果)
- 無理に活動しようとせず、回復を優先する
筆者の場合、特に日光浴の効果を強く感じました。朝や昼に10〜15分でも日差しを浴びると、夜の入眠がスムーズになり、気持ちも少し前向きになれました。
「眠気で動けない日こそ、カーテンを開けて光を浴びる」──この小さな行動が、回復への第一歩だったと今でも感じています。
まとめ
適応障害による寝すぎは、単なる疲れではなく心身が発するSOSの場合があります。
筆者も中途覚醒・早朝覚醒から始まり、日中の強烈な眠気と休日の過眠に悩まされましたが、休養と日光浴で少しずつ回復することができました。
もし寝すぎが続く、または夜眠れないのに日中極端に眠い状態が続く場合は、適応障害などメンタル不調の可能性を考え、早めに医療機関を受診してください。
眠りに異常があるときは、メンタル崩壊寸前のサインかもしれません。無理をせず、自分の体と心を守る行動を最優先にしましょう。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「朝起きれない」「やる気が出ない」「頭が働かない」── 以前の自分なら普通にできていたことが、なぜか[…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「適応障害の診断書を出したのに、会社がまともに取り合ってくれない…」 そんな悩みを抱えていませんか?[…]