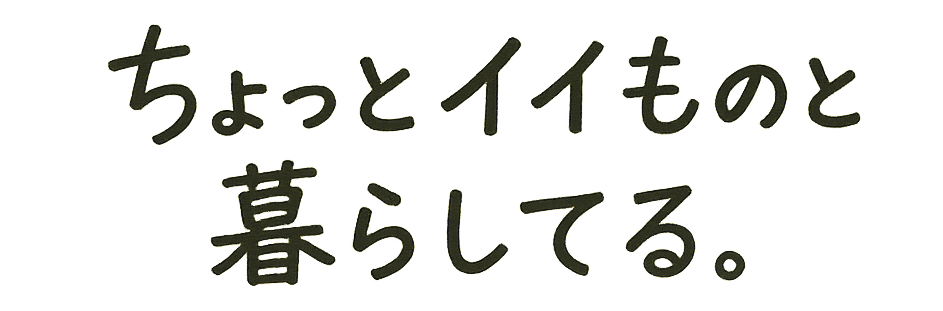「休職期間がもうすぐ終わるけど、この状態で復職できる気がしない…」
そんなふうに悩んでいませんか?
- 休職延長はそもそも可能なのか知りたい
- 医師にどう伝えれば延長してもらえるのか不安
- 実際に延長した人の事例を知りたい
結論からお伝えすると──
- 適応障害の休職延長は可能
- 延長には診断書の再発行が必須
- 延長判断で重要なのは症状の状態、とくに睡眠の安定度
この記事を読めば、休職延長の可否・医師への伝え方・注意点がわかり、安心して次のステップを選べるようになります。
適応障害の休職延長は可能【診断書は必須】
適応障害での休職は、症状が続いている場合には延長が可能です。
その際に欠かせないのが、医師による診断書の再発行です。
診断書には「休養を要する期間」や「病名」が明記され、それが会社に提出されることで延長が正式に認められます。
延長期間は1か月ごとの場合もあれば、3か月単位でまとめて発行される場合もあります。
これは医師の判断や患者の症状の安定度によって変わります。
また、会社によっては就業規則で休職の最大期間や更新単位が明確に定められています。
例えば「私傷病による休職は最長1年まで」や「診断書の更新は毎月必要」などです。
上限期間を過ぎると、自動退職となるケースもあるため、事前に人事や総務に確認しておくことが大切です。
休職延長を医師に伝えるポイント
延長を希望する場合は、診察時に「まだ復職できる自信がない」と素直に伝えましょう。
多くの医師は、患者を無理に復職させることはありません。
ただし、「自信がない」だけでは説得力に欠けるため、具体的な症状や生活の様子を説明することが重要です。
特に睡眠の状態は延長の判断材料として非常に重視されます。
- 何時間眠れているか(例:平均4時間など)
- 途中で目が覚める回数や時間
- 朝起きたときの体調や気分
診察時に口頭で説明するだけでなく、日ごとの睡眠時間や体調を簡単にメモして見せると、医師も判断しやすくなります。
スマホのメモや紙の記録など、形式は自由です。
また、気分の浮き沈みや家事・外出など日常生活に支障がある場合もあわせて伝えると、より延長の必要性が伝わります。
正直、休職を延長したいなら「睡眠がうまくとれない(中途覚醒・早朝覚醒)」さえ主張すればいけます…。
うまく睡眠がとれない状態で仕事にもとってもリスクがあるため、延長の判断がなされることが大半だと思います。
筆者の体験談
私自身も休職延長を経験しました。診察の際、医師には次のように伝えました。
- まだ睡眠が安定しておらず、熟睡できない日が多い
- 朝の目覚めが悪く、午前中は体が動かないことが多い
- この状態で復帰すれば、すぐに体調を崩す感覚がある
医師は真剣に話を聞いてくれ、「無理をすると再発のリスクが高い。では、もう1か月休みましょう」と提案してくれました。
その場で延長の診断書を作成してもらい、会社に提出しました。
診断書の再発行には数千円の費用がかかりましたが、それ以上に安心感が大きかったです。
その後も1週間ごとの受診で状態を見てもらい、延長の必要性をその都度判断している状況です。
「早く仕事に復帰しなければ」と焦らず、休職を延長して本当に良かったと思っています。
休職延長の注意点
- 診断書がなければ延長はできない(会社提出用)
- 就業規則で定められた休職の上限期間や更新ルールを必ず確認する
- 延長理由は「体調の不安定さ」を軸に説明し、特に睡眠の状態は詳細に医師と共有する
- 診断書の発行は有料(数千円)であることが多い
診断書は会社への正式な証明となるため、必ず期限内に提出しましょう。提出が遅れると「無断欠勤」と扱われてしまう場合もあります。
特に睡眠の安定度は、復職の可否を左右する大きな要素です。
「眠れていない=業務が困難」という点を、具体的な例とともに医師に共有することで、延長の判断がスムーズになります。
まとめ
- 適応障害の休職延長は診断書の再発行が必須
- 睡眠の安定は延長判断の大きなポイント
- 就業規則の上限期間や更新条件も事前に確認
休職延長は、体を回復させるための大切な選択肢です。
焦って復帰して再び体調を崩すよりも、十分に回復してから戻る方が長期的には安心です。
少しでも不安があれば、遠慮せず医師に相談し、必要なら延長を選びましょう。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 適応障害の回復期に入ったのに、昼間も夜も眠くて仕方がない…そんな不安はありませんか? 回復してき[…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 適応障害って、いつ治るの?――診断された直後や休職中に何度もよぎる、この不安。 私も同じ疑問を抱えな[…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 適応障害で休職を申し出たとき、会社はどんな対応をするべきなのか、不安に感じていませんか? 休職を[…]