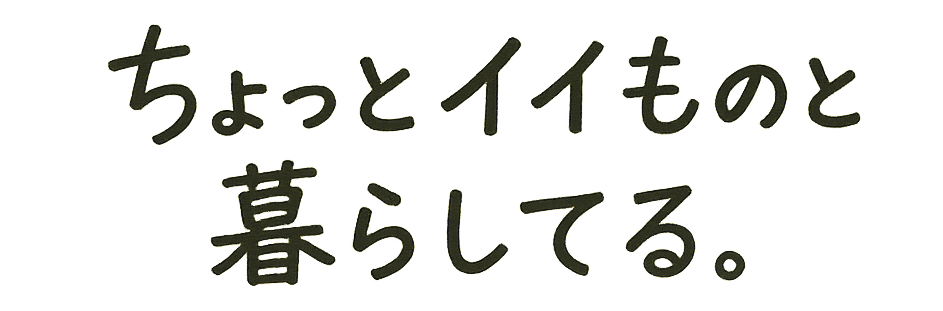愛犬のペットシーツの捨て方とニオイ対策に、こんなお悩みはありませんか?
- ペットシーツは「燃えるゴミ」で捨てていいのか、ルールがよく分からず不安になる
- ゴミの日までのあいだ、使用済みペットシーツのニオイが家に充満してしまう
- 捨てたペットシーツのニオイを徹底的に抑えられる具体的な捨て方・アイテムを知りたい
私もトイプードルを飼い始めた頃は、ペットシーツの捨て方に正解が分からず、ゴミ箱を開けるたびに「うっ…」となる日々でした。
試行錯誤を繰り返した結果、今はほとんどニオイを気にせず、ペットシーツを処理できるフローに落ち着いています。
そこでこの記事では、次のような結論をお伝えします。
- ペットシーツは「燃えるゴミ」として捨てて問題ないが、最終判断は自治体ルールの確認が必須。
- ニオイの主な原因はうんちと保管方法であり、防臭袋+専用ゴミ箱の組み合わせで解消できる。
- 専用ゴミ箱・防臭うんち袋を使えば、処理したペットシーツの匂いは完全に抑えられる
「とりあえずレジ袋に入れて普通のゴミ箱へ」から一歩進んで、ルールとアイテムをセットで整えるだけで、ペットシーツのニオイ悩みはかなり軽くなります。
ご自宅の自治体ルールや生活スタイルに合わせて、取り入れやすい形で参考にしてみてください。
結論:ペットシーツの捨て方と臭いを抑える方法
先に結論からお伝えすると、ペットシーツの捨て方と臭い対策は、次の4ステップを押さえておけば十分対応できます。
結論:ペットシーツは「燃えるゴミ」で出しつつ、うんちの密封+専用ゴミ箱+収集日までの保管ルールをセットで整えることがポイントです。

0. ぺットシーツは「燃えるゴミ」。ただし自治体ルールの確認は必須
ペットシーツは、多くの自治体で紙おむつと同じく「燃えるゴミ(可燃ごみ)」として扱われます。
ただし、細かな捨て方や注意点は自治体ごとに異なるため、最終的な区分は必ずお住まいの自治体ルールを確認してから判断することが重要です。
うんちは防臭袋で密封してからペットシーツと一緒に捨てる
ニオイの大きな原因はうんちそのものです。
トイレに流さずそのままシーツで包むのではなく、まず防臭袋に入れてしっかり結び、そのうえでペットシーツと一緒に捨てるだけで、ゴミ箱を開けたときのニオイは大きく軽減できます。
使用済みシーツは専用ゴミ箱でゴミ日まで密閉保管する
防臭袋に入れていても、通常のキッチン用ゴミ箱ではニオイ漏れが起きやすくなります。
ペットシーツやおむつ専用の密閉ゴミ箱を使い、使用済みシーツはすべてそこに集約してゴミの日まで保管することで、リビングやキッチンへのニオイ拡散をほぼ防ぐことができます。
燃えるゴミの日に指定袋で廃棄する
ゴミ収集日に、専用ゴミ箱の中身を取り出し、自治体指定の燃えるゴミ袋にまとめて入れてしっかり口を縛ります。
「専用ゴミ箱で密閉保管 → 収集日にまとめて燃えるゴミとして出す」という流れをルール化することで、毎日のニオイストレスを最小限にできます。
ペットシーツは何ゴミ?まずは自治体ルールをチェック
ペットシーツは、多くの自治体で紙おむつと同じ「燃えるゴミ(可燃ごみ)」扱いになっています。
ただし、細かいルールは地域によって異なるため、「全国共通で絶対こう」とは言い切れないのが実情です。
多くの自治体では「燃えるゴミ」扱いが一般的
一般的には、犬や猫のペットシーツは、
- 家庭から出る紙おむつ・生理用品などと同じカテゴリ
- 専用の分別はなく、通常の「燃えるゴミ」として指定袋へ
という扱いになっているケースが多いです。「紙おむつ=燃えるゴミ」となっていれば、ペットシーツも同じ扱いである可能性が高いと考えて問題ありません。
最終判断は自治体サイト・窓口で必ず確認しておく
とはいえ、トイレに流せるタイプのシーツや猫砂など、例外的な扱いになっているケースもあります。安心して捨てるためには、次のような手順で確認しておくのがおすすめです。
- お住まいの自治体サイトで「ごみの分別一覧」「家庭ごみの出し方」を確認する
- 「紙おむつ」「ペットのふん」「ペットシーツ」などの項目をチェックする
- 不明点があれば、環境担当課やごみ収集窓口に一度電話で聞いておく
「うちの地域ではこの捨て方でOK」と自信を持てる状態にしておくと、毎日の処理も安心して続けられます。
我が家の「完全防臭」ペットシーツ捨て方フロー
ここからは、私が実際に行っているペットシーツの捨て方を、アイテム選びも含めてフローで整理します。
「どの順番で・何を使って・どう捨てるか」を決めてしまうと、毎日の処理が一気にラクになります。
① ペットシーツは薄型・大容量で「こまめに交換できる体制」を作る
ニオイ対策の基本は、汚れたシーツを放置しないことです。
そのため、我が家では「高級シーツを長く使う」よりも、薄型・大容量タイプをこまめに替える前提で運用しています。
薄型大容量でおすすめのペットシーツ(フリーリー 薄型 レギュラー200枚)
普段使いの一軍として使っているのが、「フリーリー ペットシーツ 薄型 レギュラー 200枚」です。
トイプードルなどの小型犬であれば、
- 1回分のオシッコなら吸収力は十分
- 薄型なのでゴミのかさも増えにくい
- 枚数が多く、「ちょっと汚れたらすぐ交換」しても罪悪感が少ない
といったメリットがあります。ニオイを抑えるには「厚さ」よりも「交換頻度」を優先するイメージです。
ペットシーツはふるさと納税でまとめて入手するのもおすすめ
消耗が激しいご家庭であれば、ふるさと納税品を活用して大量にペットシーツを入手するのも有効です。
- 常にストックに余裕がある状態を作れる
- 「もったいないから交換を我慢する」が起きにくい
- 結果として、こまめな交換 → ニオイ源を早く処理できる
シーツ在庫に余裕を持たせておくこと自体が、ニオイ対策の一部と考えると、ふるさと納税との相性はかなり良いです。
② 使用済みシーツはペッツバリュー「パッドロッカー」にまとめて捨てる
次のポイントは、使用済みシーツの「行き先」を固定することです。
普通のゴミ箱ではどうしてもニオイが漏れやすいため、我が家でペットシーツ専用ゴミ箱「ペッツバリュー パッドロッカー」に集約しています。
ペットシーツ専用ゴミ箱「パッドロッカー」を選ぶメリット
- 専用フィルムで中身をねじりながら包む構造で、ニオイが漏れにくい
- フタ+フィルムの二重バリアで、リビングに置いてもニオイが気になりにくい
- 「ペットのトイレごみはここに捨てる」と場所が決まるので、家族全員の動きが統一される
「どのゴミ箱に入れるか」を迷わないようにするだけでも、日々の小さなストレスが減ります。
パッドロッカーを使ったニオイを抑える捨て方の流れ
我が家では、次のようなルーティンにしています。
- 1. トイレ掃除のタイミングで、汚れたシーツをはがす
- 2. うんちがある場合は、防臭袋に先に入れておく(詳細は③で解説)
- 3. 新しいシーツをセットしたあと、古いシーツ+防臭袋をパッドロッカーへ投入
- 4. フィルムの中に落とし込み、ニオイ源を密閉
これを習慣化すると、「シーツ交換=ニオイ対策まで一度に完了」するので非常にラクです。
③ うんちは「うんちの臭いバリア袋」でしっかり密封する
ニオイの元凶であるうんちは、シーツと一緒にそのまま捨てず、必ず防臭袋でワンクッション置くのがポイントです。
マンダリンブラザーズ「うんちの臭いバリア袋」の防臭性能
我が家では「マンダリンブラザーズ うんちの臭いバリア袋」を使っています。
特徴としては、
- 袋に適度な厚みがあり、袋から匂いが漏れ出てくることがない
- 口をねじって固結びすると、鼻を近づけても全く臭いを感じない
使い方はシンプルで、
- シーツの上のうんちだけ回収 → バリア袋に入れる
- 袋の口をしっかりねじってから固結び
- その袋をペットシーツと一緒にパッドロッカーへ投入
「うんち → 防臭袋 → パッドロッカー」という二段構えにすることで、ニオイ対策のレベルが一気に上がります。
室内・散歩中どちらでも使いやすいポイント
この防臭袋は、室内だけでなく散歩中のうんち処理袋としてもそのまま使えるのが便利です。
- 散歩中に回収したうんちも、同じ袋に入れて持ち帰る
- 帰宅後はそのままパッドロッカーに投入するだけ
袋をシーンで分けなくて良いので、在庫管理もシンプルですし、「うっかり普通のビニール袋で持ち帰って、家が臭くなる」というミスも防げます。
④ 最後は指定袋でゴミ収集日に出す
最後のステップは、専用ゴミ箱の中身をどう外に出すかです。
ここをきちんと決めておくと、ゴミ出しの日もバタつきません。
ゴミ収集日までの保管場所とタイミングの工夫
- 基本は、燃えるゴミ収集日の朝にパッドロッカーの中身を取り出す
- フィルムに包まれた“シーツのかたまり”を、そのまま指定袋に入れる
- 他のキッチンの燃えるゴミも同じ袋にまとめて、しっかり口を縛る
夏場などニオイが出やすい時期は、
- 前日の夜にパッドロッカーの袋をゴミ袋へ移し、玄関やベランダなど比較的涼しい場所に一時保管
といった形にすると、室内にニオイを残しにくくなります。
ゴミ出し時にニオイを残さないためのちょっとしたコツ
- 袋の口を二重にねじってから結ぶ(可能なら二重結び)
- パッドロッカー本体は、中身を空にしたタイミングでアルコールスプレー+ペーパーでサッと拭く
「こまめなシーツ交換」+「防臭袋」+「専用ゴミ箱」+「ゴミ出しのルール」をセットにすることで、ペットシーツのニオイ悩みはかなりコントロールしやすくなります。
まとめ:捨て方+防臭アイテムでニオイ悩みは解消できる
ペットシーツのニオイ問題は、「どこに捨てるか」だけでなく、どんなアイテムを使って・どんな手順で処理するかをセットで見直すことで、かなりコントロールしやすくなります。
この記事でお伝えしたポイントをあらためて整理すると、次の4つです。
- ペットシーツは基本「燃えるゴミ」だが、最終判断は必ず自治体ルールを確認する
- うんちは防臭袋でしっかり密封してから、ペットシーツと一緒に捨てる
- 使用済みシーツは、普通のゴミ箱ではなく専用ゴミ箱でゴミ日まで密閉保管する
- 薄型・大容量シーツで「こまめに交換できる体制」を作り、ニオイ源を放置しない
特に、
- 薄型・大容量タイプのペットシーツ(+ふるさと納税でストック確保)
- ペットシーツ専用ゴミ箱「パッドロッカー」
- マンダリンブラザーズ「うんちの臭いバリア袋」
この3つを組み合わせることで、「こまめに交換しても負担にならない」「ゴミ箱からニオイが漏れない」環境がつくりやすくなります。
ペットとの暮らしは、どうしてもニオイと隣り合わせですが、捨て方とアイテム選びを少し工夫するだけで、日常のストレスは大きく減らせます。
ご自宅の自治体ルールや生活スタイルに合わせて、ぜひ取り入れやすいところから試してみてください。