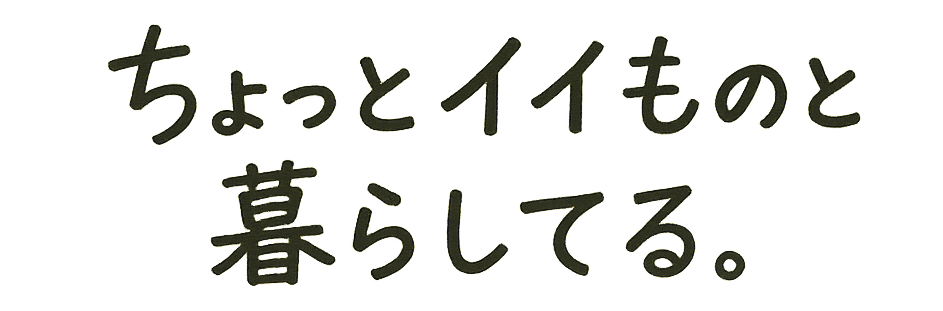「環境の変化で心身が限界…でも、どこで診断してもらえばいいの?」
そんなふうに悩んでいませんか?
- 何科を受診すれば適応障害かどうかわかるのか知りたい
- どんな症状が診断の目安になるのか不安
- 受診時にどう説明すれば診断につながるのか迷っている
結論からお伝えすると──
- 適応障害は心療内科や精神科で診断されるのが基本
- 診断には症状とストレス要因の明確さが重要
- 受診前に症状や経過を整理しておくと診断がスムーズ
この記事を読めば、病院選びの迷いがなくなり、自分の症状を的確に伝える準備ができ、
診断から治療までの流れがスムーズになります。
適応障害はどこで診断される?
適応障害は、主に心療内科や精神科で診断されます。
これらの診療科は、ストレスによる心身の不調を専門的に診る医師が在籍しているため、
症状や背景を総合的に判断してくれます。
ただし、近くに心療内科や精神科がない場合は内科でも一次的な診断や紹介状の発行が可能です。
まずは受診し、必要に応じて専門医へ紹介してもらいましょう。
また、以下のような緊急性の高い症状がある場合は、救急搬送も視野に入れるべきです。
- 強い希死念慮や自傷行為の衝動がある
- 極端な不眠や動悸で日常生活が困難
- 会話や行動が急激に乱れる
どんな症状で診断される?
適応障害の診断は、症状だけでなく発症のきっかけや時期も重要です。
一般的には、明確なストレス要因があり、その後3か月以内に症状が出るケースが多いです。
主な症状は以下の通りです。
精神的な症状
- 不安感や焦り
- 抑うつ気分、涙もろさ
- 集中力の低下
身体的な症状
- 不眠(中途覚醒・早朝覚醒など)
- 食欲不振
- 頭痛や動悸
うつ病や不安障害との違いは、原因となる出来事が明確であり、そのストレスから離れると症状が軽減しやすい点です。
筆者が診断されたときの症状(体験談)
私が心療内科を受診したのは、仕事での人間関係が原因でした。具体的には、以下のような症状がありました。
- 中途覚醒や早朝覚醒が続き、熟睡できない
- 明確に上司の言動が原因でストレスを抱えている
- 仕事でメールを読んでも内容が頭に入らない
- 出勤時に体が思うように動かない
- 話す内容が頭から抜け落ちる
- 休日は元気だが、仕事が近づくと体が重くなる
受診後、医師から「特定のストレス源が原因で心身に症状が出ている」と説明され、適応障害と診断されました。
診断までの流れと準備
適応障害の診断は、問診と症状の経過確認が中心です。初診時には以下の準備をしておくとスムーズです。
- 保険証、お薬手帳
- 症状が出始めた時期と経過をメモ
- 症状が出る場面やきっかけの記録
医師は「いつから」「どんなきっかけで」「どのような症状がどのくらいの頻度で出ているか」を重視します。
可能であれば家族や職場の証言も診断材料になります。
診断後にできること
診断がついたら、治療と生活環境の調整を進めます。
- 薬物療法(睡眠薬や抗不安薬など)
- カウンセリングや認知行動療法
- 休職や業務量の調整
また、診断書を取得すれば、会社への正式な休職申請や就業配慮を受けやすくなります。
まとめ
- 適応障害は心療内科や精神科が診断の専門
- 診断には症状とストレス要因の明確さが重要
- 受診前に症状や経過を整理しておくと診断がスムーズ
一人で抱え込まず、少しでも異常を感じたら早めに専門医へ相談しましょう。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 適応障害が治りかけてきたけれど、本当に回復しているのか不安…そんな悩みはありませんか? 治り[…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「適応障害で咳が出るのは病気の症状?それとも偶然?」そんな疑問を持つ方は少なくありません。 普段は出[…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 話したいのに言葉が出てこない。頭が真っ白になる。脳に靄がかかったようで会話ができない──。適応障害の症[…]